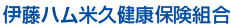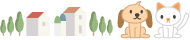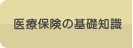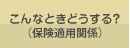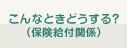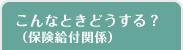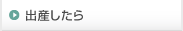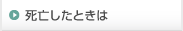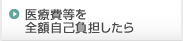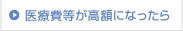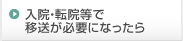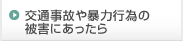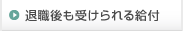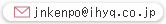「健康保険限度額適用認定証」とは? 高額療養費制度では、受診者が医療費の自己負担額(医療費総額の3割または2割)を医療機関の窓口で支払った後、自己負担限度額を超えた額が還付されます。しかし、がん治療などの高額な外来診療を受けたり長期入院した場合、窓口での一時的な負担が大きくなることがあります。このとき、医療機関に「健康保険限度額適用認定証」(以下、「限度額適用認定証」)を提示すると、受診者は窓口で自己負担限度額だけを支払えばよいことになります。 マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要で、限度額までの支払いが可能となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。 限度額適用認定証が必要となる場合
70歳以上の限度額適用認定証について お手元の高齢受給者証または資格確認書をご確認いただき以下①②に該当する方は申請不要です。健康保険証と高齢受給者証または資格確認書を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。 申請方法 「健康保険限度額適用認定申請書」を記入し、健康保険組合へ提出してください。後日健康保険組合より「限度額適用認定証」を交付します。 注意事項 「限度額適用認定証」の発効年月日は、申請書が健康保険組合に受付された日の属する月の初日となります。 次に該当する場合は「限度額適用認定証」を返納してください。 有効期限に達したとき、被保険者の所得の変動により適用区分が変わるとき、異動により被保険者等記号・番号が変わったときに引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度申請を行ってください。 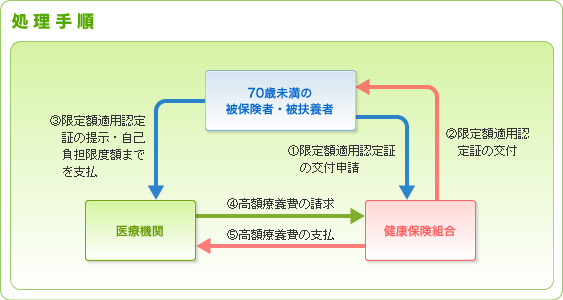 |
- ページ内を移動するためのリンクです。
HOME > こんなときどうする?(保険給付関係) > 医療費が高額になったら